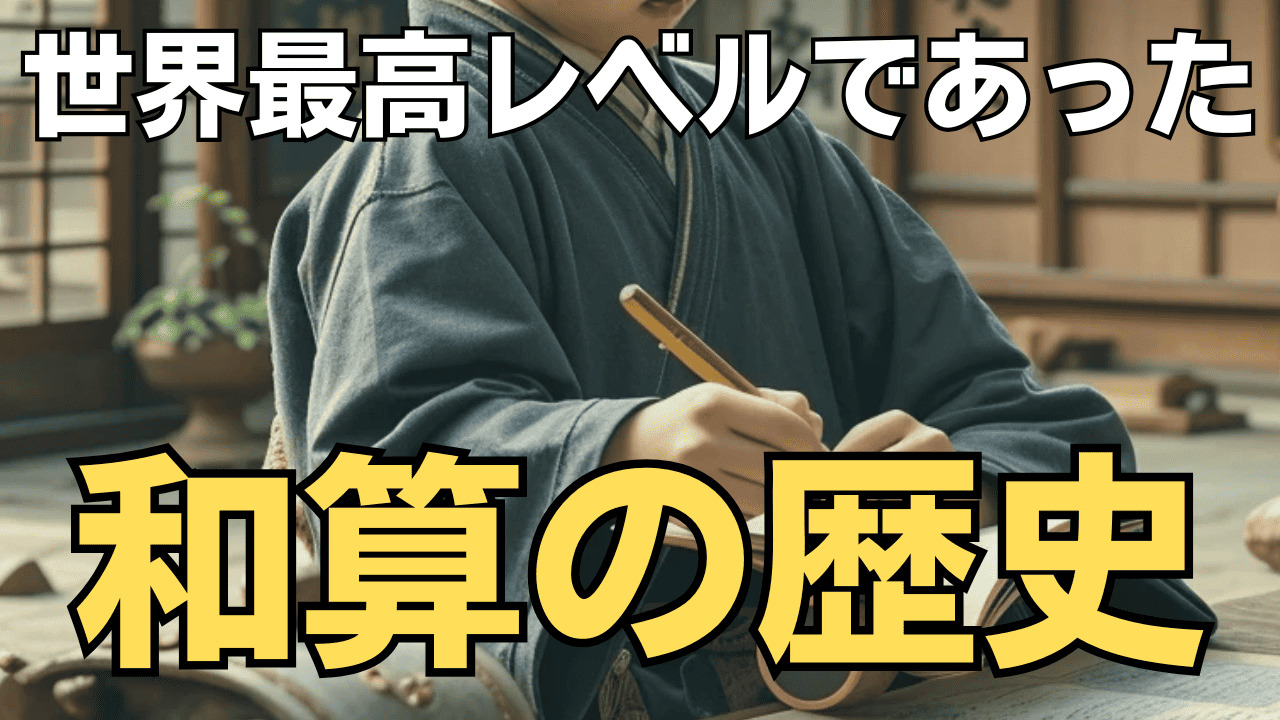和算ってどんなもの?
油分け算
問「桶に油が十升入っている。これを7升ますと3升ますを使って5升ずつに分けよ」

5升にするためには2升をどう作るかを考えるのがポイントですかね・・・
答えはChatGPTとかで調べれば出るので、興味あるかたはお調べください!
盗人算
問「数人の盗人が盗んできた布を山分けしようとしている。1人7反ずつ分ければ6反あまり、8反ずつ分ければ9反不足する。盗人と反物のかずはいくらか」

現代だと方程式で解けば割と簡単にできます。
盗人の数をXとして、7X+6=8X-9みたいな感じで・・・
ただ当時は図を使って解答していたみたいです。
横を盗人の数、たてを一人に配る反物の数・・・みたいな感じで。
円規(こんはす)の術
図形を描く道具は現在と同じ定規やコンパスを使用していた。
なお、作図法のことを円規の術と呼んでいた。
正方形の書き方や正三角形の書き方など現代とあまり変わらないものであった。

ちなみにコンパスは「ぶん廻し」とも言われていました。
文字通りですね(笑)
和算のはじまり
日本における記録上のもっとも古い数学の資料は奈良時代からあったとされる。
中国唐の制度をまねて算博士を置いた記述が残っている。
また、数学の教科書も唐からの書物を使っていた。
しかし、そこからしばらくの間、日本で数学が発展を遂げることはなかった。
戦国時代が終わり江戸時代になると平和な世の中になった。
平和な世の中になると、武芸(戦争)ではなく経済(計算)が重要になってくる
そのため次第にそろばん塾などが繁盛するようになる
しかし、日本は鎖国政策により海外の情報はほとんど入ってこない状態であった。
明治維新までの間、日本の数学は独自の進化を遂げることとなる。
元々日本人は読み書きができるのが当たり前であったこともあり、
一般人にいたるまで学問が当然のように浸透していた背景も和算発展の一役を買っている。

★欧米系の数学と違うところ
欧米系数学は自然科学の発展に伴い必要であったため発展しました。
日本の和算はどちらかというと楽しみのための算術書も多く遊芸的なものに近いと言われます。
そのため専門家だけでなく一般庶民にいたるまで算術が広まったとされています。
しかし遊芸的とは言え、学問のレベルは欧米系の数学に全く引けを取っていません。
欧米よりも早く発見された数学の公式があったり、現在の高校や大学で学ぶようなレベルにまで到達してました。
著名な和算家たちの登場
毛利重能
「割り算天下一」のキャッチコピーで多くの塾生を集めていた
1622年に『割算の書』を書いた
この割算の書は最も古い和算書の1つと言われる
数々の功績から日本数学の祖と呼ばれるようになる
吉田光由
中国の数学書『算法統宗』を学び、日本人向けに改良
☞1627年『塵劫記』という数学書を出版
教科書のような説明的な書き方ではなく読み物風に書かれていることが特徴
九九の表、そろばんを使った計算方法、それらを使いこなす練習問題が掲載された
そのため多くの人から指示されてベストセラーとなった

この塵劫記が和算の基礎を築いたと言われます
その後多くの改訂版が出版されることになり
絵が挿入されたり「ねずみ算」「ままこだて」などのパズル問題も入った
塵劫記のベストセラー効果で一般人の数学的素養は高まることになった
物の売り買いだけでなく、技術発展にもつながっていくことになった
たとえば測量、天文、暦学などに応用されていった。
そしてそのこと各々の学問における専門家の登場も促した。

伊能忠敬なんかも測量・天文の専門家であり、影響を受けたと思います。
関孝和
江戸時代前期の日本を代表する数学者。
独自に「円理」や「筆算術」を発展させ、西洋よりも早く「行列式」や「高次方程式の解法」に相当する理論を考案した。
弟子の活躍により和算が全国に広まり、日本数学の基礎を築いた人物として高く評価されている。

この後出てくる最大の流派「関流」の始祖ですね。
和算の特徴
偉題継承
吉田光由が書いた塵劫記は何回も改訂された
1641年の改訂版で巻末に解答をつけない問題を12問載せ、世の中の算師に「といてみよ」と挑戦させた

このような問題を「偉題」と言います。
その偉大が継承されていくから偉大継承なんですね。
偉題を解いた人がさらに自分で難問を作り、
その答えを付けずに出版する・・・・次第にこのような風潮が生まれた

そもそも何で吉田光由はこんなことをしたのか?
それは塵劫記の人気が上がるなかで海賊版やレベルの低い塾が生まれたことが大きいと言われます。その対策として偉題を載せることにしたと言っております。
以下は吉田光由の言葉です。
「最近、算術の達人が増えてきたが、一般の人は彼らの実力を見分けがたい。そこで算術の先生の実力を見極めるために、今ここに答えを除いた12問を提出する。算法の達人ならば解答を公表してみよ」

★放送では言ってないけど王道の流れをご参考までに・・・
塵劫記(改訂版1641)→参両録(1653)→算法闕疑抄(1659)→童介抄(1664)→算法根源記(1669)→古今算法記(1671)→発微算法(1674)
古今算法記の偉題が超難問であったが、関 孝和が解いて『発微算法』を発表しました。
さすが算聖と呼ばれた人ですね。
その後塵劫記をまねた亜流本がどんどん出回ることになる
○○塵劫記であったり塵劫記××など・・・
こういったものだけでも400種類はあると言われている
流派
遊芸的であった和算は、茶道や華道にどちらかと言うと似ている要素がある
茶道や華道には流派が存在するように、和算にも流派が存在していた

答えが同じになる算術に流派はおかしい気はしますが・・・解き方や使用する記号が違っており、流派間で競い合っていたようです。
最大の流派は算数の神様と呼ばれる関 孝和を師匠とする関流
他にも最上流、中西流、宮城流、宅間流など数多く存在した
これらの流派の塾に入って算法が上達すると免許が与えられた
→免許が与えられることで一定の名誉も得ることができた
算額奉納
絵馬に近いもので和算の問題を解いてその問題や答えを神社仏閣に奉納した
★ご参考までに【絵馬について】
元々は馬を奉納していたが、それが木に描いた馬に変わり健康、安産、無病息災などの願い事を書くようになった
現在確認できるものだけでも1000近い算額がある

神社や仏閣に行ったときに円や三角の図形がある絵馬があったら多分それですね。
17世紀中ごろからこのような風習が生まれたとされる
諸説あるが大半は自慢のためという説が割と有力
中には奉納理由がきちんと書かれているものもある(病気になったが治った、普段やっている算法の絵馬で神にお礼を伝えたい・・・など)
最後に

関流を代表する和算家・藤田貞資が書いた『精要算法』(1781)に記載されている言葉です。
個人的にはぶっ刺さりましたので紹介します。
近頃の算術には「用の用」「無用の用」「無用の無用」がある。
「用の用」とは世の中の役に立つ全てである。
「無用の用」とはすぐさま役に立つものではないが、勉強することによっていずれは役立つものの助けとなるものである。
「無用の無用」とは最近の算術の本に見られるように、問題のための問題、いたずらに奇妙にした問題、ことさらに複雑にした問題などをつくり、自分の奇行を誇らしげに自慢しているもので無駄なことだ。