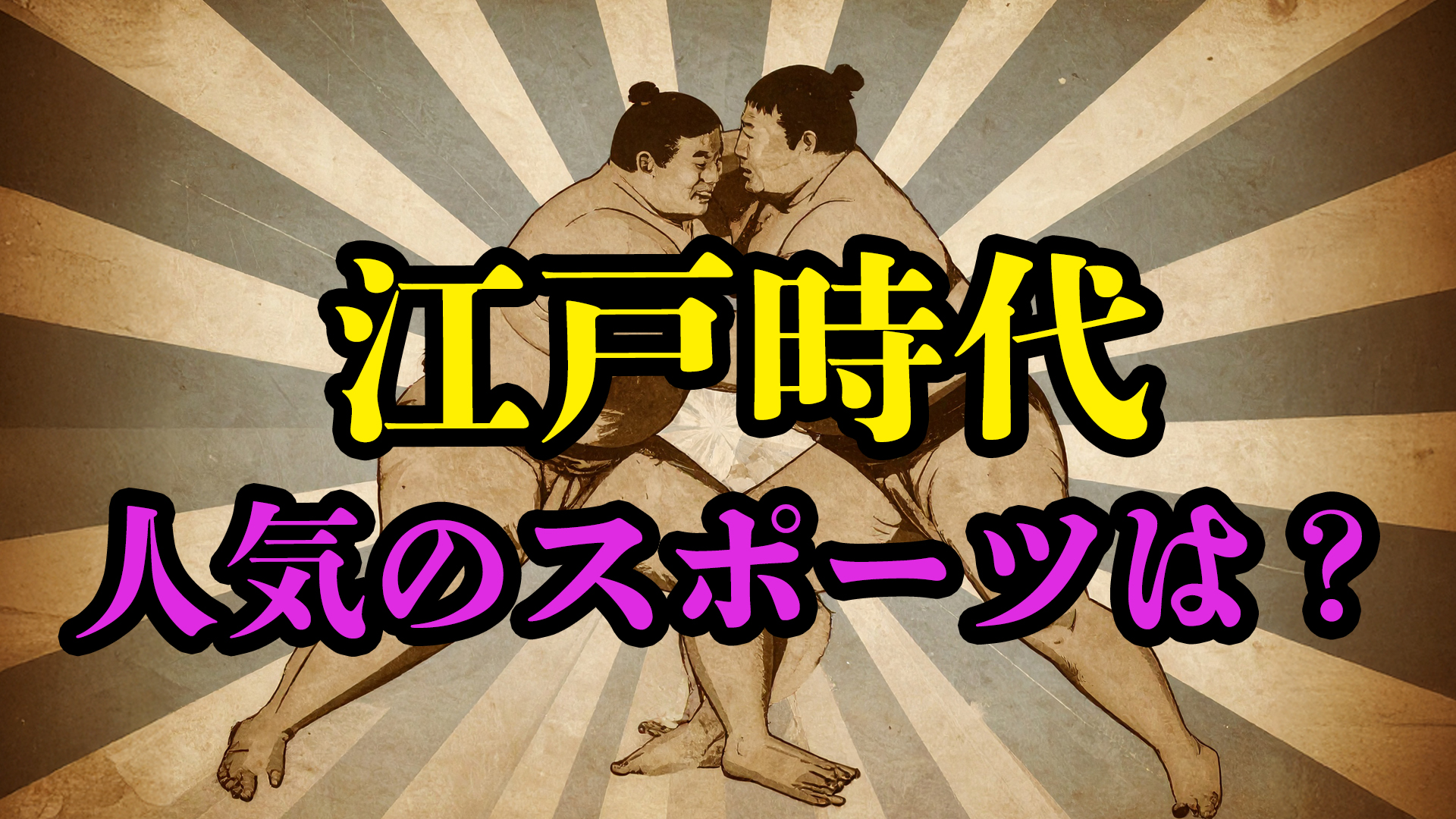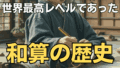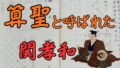スポーツの歴史 ― 江戸のスポーツ
「スポーツ」という言葉の語源は、ラテン語の 「deportare(デポルターレ)」、つまり「気分転換」を意味します。
スポーツ文化が特に発展したのは古代ギリシアで、さまざまな競技が開催されました。これが現在の競技性のある運動、オリンピック競技の原型となりました。
日本初のスポーツ競技会
明治7年(1874年)、東京の海軍兵学寮で行われた「遊戯会(運動会)」が日本最初のスポーツ競技会とされています。イギリスから指導者を招いて実施されました。
日本は明治以降、西洋文明を積極的に取り入れ、西洋式のスポーツ ― 野球・サッカー・テニスなど ― が普及していきます。
西洋スポーツ以前の日本の運動文化
しかし、西洋のスポーツが入る前から、日本にも独自のスポーツ的な文化が存在していました。
相撲の起源
『古事記』には神々が力比べをしたという記述があり、これが相撲の原型とされています。「相撲をとる」という言葉は、神々が「手を取って」力比べをしたことに由来します。
武士の訓練
鎌倉時代以降、武士は戦いの訓練として剣術・馬術・弓術を学びました。戦国時代が終わり平和な江戸時代になると、娯楽としての要素が加わり、庶民にも遊びや運動が広まっていきました。
江戸の遊びと運動文化
かけくらべ(短距離走)
江戸時代には子どもの遊びとして人気がありました。時間を計る道具がないため、同時にスタートして先にゴールした方が勝ちという単純なルールでした。
しかし、大人の競技には発展せず、走ることは「飛脚」や「駕籠かき」など特定の職業の人だけの技能でした。
なんば走り・なんば歩き
同じ側の手足を同時に出す走法。体をひねらず腰から下で走るため、長時間走っても疲れにくく、荷物を持っても安定しました。1日に100〜200km走ったという記録も残っています。
登山者の中には体力消耗を防ぐため、「なんば歩き」に近い歩き方をする人もいます。
走る文化が発達しなかった理由
- 服装が着物(長着)で走りにくかった
- 草履を履いていたため動きに制限があった
- 武士は刀を腰に差していた
普段走ることが少ない社会は、平和で幸せな社会だったのかもしれません。
竹馬
現在の竹竿に足場をつけた竹馬は19世紀前半に登場。さらに古い時代には、笹竹にまたがって走る遊びもありました。ヨーロッパの訪問者が驚いた記録もあります。
日本人の「なんば」の動き(同じ手足を出す)と竹馬の操作が合っていたため、竹馬は自然に日本に定着しました。
穴一(あないち)
地面に穴を掘り、銭や貝殻を投げ入れる遊び。江戸時代には賭博の対象となり、幕府から禁止令が出るほど流行しました。のちのメンコの原型とされています。
ようきゅう(弓競技)
中国から伝わった宮廷行事が庶民の娯楽に。江戸では「矢場」で的を射る競技が盛んに行われ、年に2回の大会もありました。人気の理由には「矢場女(やばめ)」と呼ばれる女性の存在もありました。
相撲の種類
- 勧進相撲: 見物料を払って楽しむ職業相撲。各藩が力士を抱え藩の威信を競った。
- 辻相撲: 路上で行われるアマチュア相撲。人気が高すぎて幕府が禁止するほど。
- 一人相撲: 一人で行司・力士を演じる芸。投げ銭で勝敗を決めるパフォーマンス。今も愛媛・大山祇神社で「ひとりずもう」として行われている。
力石
重い石を持ち上げて競う力試し。「石ざし」「いしかつぎ」「石回し」「石運び」などの種目がありました。寺社の境内で行われ、今でも多くの力石が保存されています。
水術
日本は水に囲まれた地形のため、水術(泳法)が武士を中心に発達。隅田川などに水練場が設けられました。
- へいたい: 平泳ぎに似た泳ぎ。クロールは敵を見失うため発達せず。
- 立ち泳ぎ(立体): 垂直姿勢で泳ぐ技術。シンクロの原型のような泳法。
日本選手が平泳ぎで強いのは、この伝統的な泳法の影響なのか??
まとめ
西洋式のスポーツが入る以前から、日本には独自の「スポーツ」や「遊び」の文化が存在していました。こうした長い歴史の積み重ねの上に、現在のスポーツ文化が築かれています。