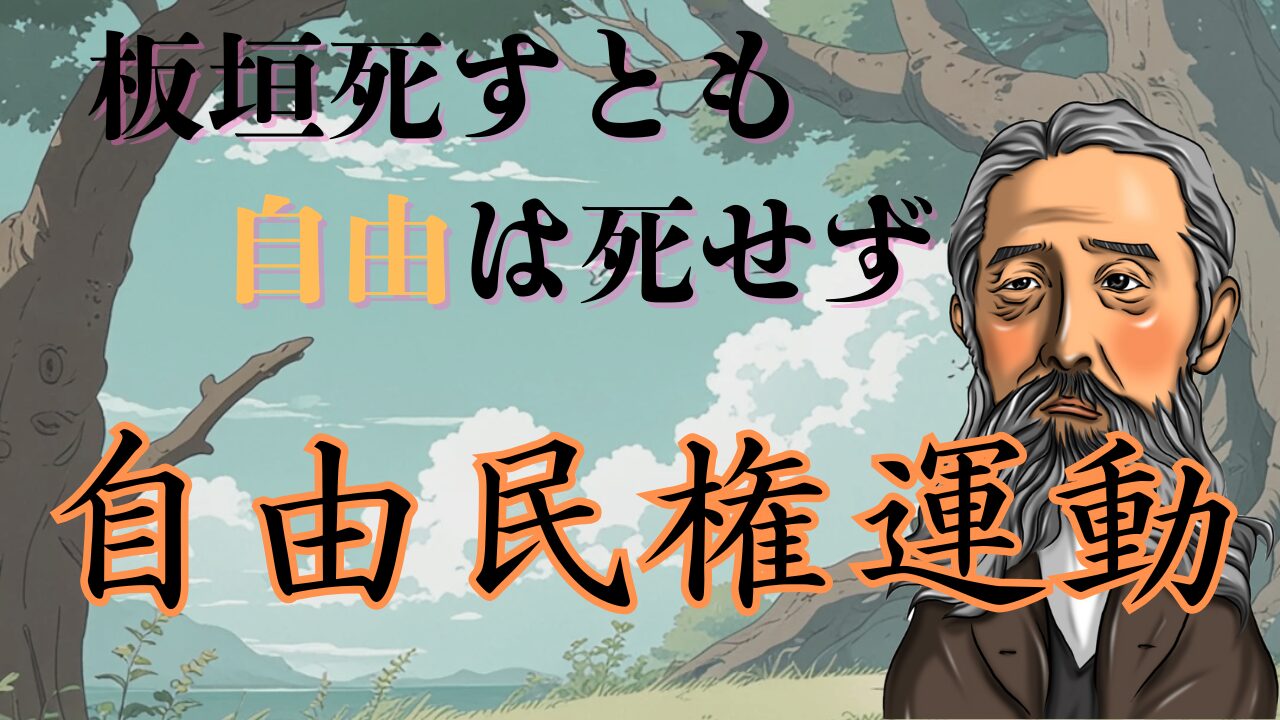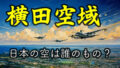「板垣死すとも自由は死せず」
明治15年(1882年)4月に板垣退助は、岐阜県で刺客によって襲撃され、
この言葉を発したと言われています。
この言葉は、自由民権運動を象徴するものとして瞬く間に有名となりました。
自由民権運動とは

文字通り自由で民主的な国を目指そうとする運動のことです。
逆に言えば、それまでの日本は自由で民主的な国ではなかったということです。
例えば江戸時代までは身分制度もありましたし、職業も世襲がほとんどでした。
自由民権運動のはじまり
岩倉使節団が欧米訪問している間
留守政府により民選議院の設置が政権内で取り上げられていた
岩倉使節団が帰ってきて明治六年の政変が起こる
→征韓論で明治政府が分裂した
西郷隆盛や江藤新平は武力で国を変えようとしたが鎮圧されてしまう
板垣退助は言論で政治を変えなくてはいけないと考える
板垣退助は政府を辞めた人々を集めて愛国公党(政治結社)を結成
政府に民選議員設立建白書を提出

当時の政治は一握りの役人が牛耳っているため、
国会を開いて国民を政治に参加させることを目的としました
★国会
選挙で選ばれた人が法律を作る場所
つまり国民みんなで法律を決められる
←しかし明治政府は自分たちに都合のいい法律を作っている
しかし政府は民選議員設立建白書を却下する
国民が政治に参加するのは早いと考えたため
しかし新聞に民選議員設立建白書が載る
日本中にその存在が知れ渡ることになった
また、国民の中で議論が巻き起こる

民選議員設立建白書は国民の権利を要求するものだから肯定的な意見が目立ちそうですが、批判も多かったようです。
そしてこの民選議員設立建白書の批評がさらに記事になって・・・
こうして国民の中で政治に対する関心が高まることになる
立志社の設立
板垣退助ら愛国公党のメンバーは自分らの故郷に帰る
高知で新たな政治結社「立志社」を設立
講演会をひらき、人権や自由の大切さを国民に訴える
この政治結社設立の動きが全国へ拡大することで
自由民権運動へとつながっていく
愛国社の設立
バラバラであった各地の政治結社を全国組織としてまとめていく動きが起こる
→「愛国社」の設立
しかし、ここで政府の妨害が入った
政府からすれば自由民権運動は邪魔なもの

自分たちの思うように政治ができなくなってしまうからです。
愛国社の主要メンバーを手なずけてしまおうと考えた政府は、
板垣退助らに対して国会設立と憲法作成の約束をする
その代わり明治政府に戻ることを要求する
☞板垣は政府に帰ってしまう
☞愛国社は事実上分裂して崩壊
☞しかも板垣はすぐ大久保利通や木戸孝允と対立し辞めてしまう
自由民権運動の抑え込み
1875年 讒謗律、新聞紙条例、出版条例の改正
☞言論・出版を取り締まる法令
政府批判を徹底的に取締ることで民権派を弾圧
また、1877年に西南戦争が勃発し鎮圧される
このことから武力での政治変革は無理だということを国民が理解し始める
→暴力ではなく言論で政府と戦う必要がある
自由民権運動の再興
立志社が「立志社建白」を政府に出す
・国会開設
・条約改正
・地租軽減
☞政府は却下
☞しかしまたしてもマスメディアによって国民が知ることになる
☞国民は立志社建白を支持する
そして愛国社を再興させた
地方の有力者たちも愛国社に加わっていくことになる
地主や豪農が支持層となった
力を付けた愛国社は政府に国会設立の期限を迫るようになる
愛国社→国会期成同盟へと名前を変える
そして国会開設の署名活動を行う
しかし政府も再度弾圧をする
☞1880年 集会条例・・・集会・結社の自由を規制
政治に関する集会を行う際は事前申請が必要
国会期成同盟の行った署名活動にはそこまで影響はなく
政府に対して国会開設の署名を送り付けた
しかし、政府はこれを却下する

自由民権運動は度重なる政府からの弾圧を潜り抜け、
最終的には国会開設へと繋がっていくんですが、
民権を勝ち取るのには多くの犠牲や先人の尽力があったからこそなんですね。