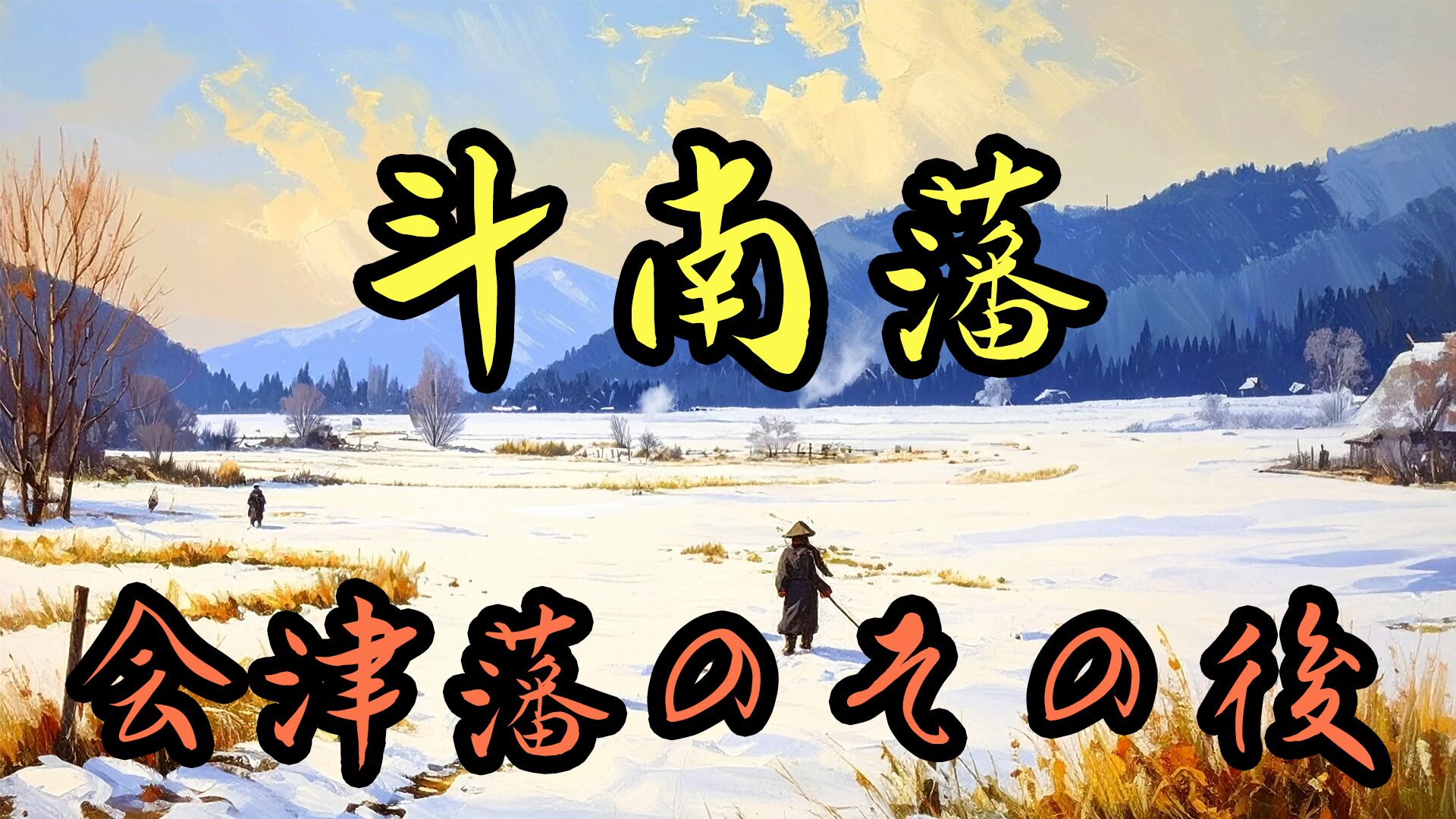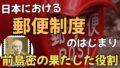斗南藩(となみはん)
●斗南までの流れ
幕末の会津藩は薩摩藩・長州藩と並ぶ大きな勢力を築いていました。
戊辰戦争が起こり、会津は朝敵として徹底的に狙われます。恭順の意を示したものの攻撃を受け、会津戦争で敗北しました。
その後、会津藩士は新潟や東京で謹慎となり、1869年に会津松平家の再興が許され、旧南部藩領の一部3万石が与えられて斗南藩が成立します。
●斗南藩の領地と実態
- 現在の青森県むつ市・三沢市・十和田市にまたがる飛び地
- 旧会津藩28万石 → 3万石へ
- 不毛の地で実収は7千石ほど
- 風雪が激しく、米はほとんど育たず雑穀中心
凶作や飢餓の歴史があり、記録には餓死や人肉食の悲惨な事例も残されています。
●移住の現実
約17,000人の会津藩士とその家族が移住。
明治政府からの十分な支援もなく「移住しなければ処分」と迫られていました。
移住者は子供や高齢者、傷病者も多く、会津から斗南まで約600kmを3週間かけて北上した人もいました。
●厳しい生活
冬は氷点下10〜20度、食糧も布団も乏しく、ワラビの根や海藻、時には犬の肉まで食べて命をつなぎました。
不衛生な環境で病人が続出。半年間で約2,400人が病に倒れました。
地元民からは「会津のゲダカ(毛虫)」と蔑まれることもありました。
●指導者と政策
運営の中心は大参事・山川浩、小参事・広沢安任、永岡久茂。
山川は若き会津藩家老で行動力と人望を持っていました。
- 移住後すぐに廃刀令を実施 → 武士と農民の溝を防ぐため
- 1870年 斗南藩校「日新館」開設 → しかし子供は食料確保に追われ通えず
- 救貧所を設け、はた織りや紙すきなど職業訓練も実施
●廃藩置県とその後
1871年の廃藩置県で斗南県→弘前県→青森県に合併。
斗南藩はわずか1年半で消滅しました。
移住の自由が認められ、多くは会津や東京へ戻る一方、青森に残った士族もいました。
●斗南藩士の成果
- 広沢安任 → 日本初の民間洋式牧場「開牧社」を三沢市に設立。牧畜文化の先駆けとなる。
- 教育者としても活躍し、青森の教育基盤づくりに貢献。
●まとめ
斗南藩は短命に終わったものの、その存在は会津藩士にとって苦難の象徴でした。
明治維新の「明るい改革」の裏で、多くの犠牲と苦しみがあった事実を忘れてはいけません。
「明治維新は多くの人々の尊い犠牲のもとに成立したのであって、決して無欠革命ではない」
― イギリス公使 パークス

おが太郎
今回の参考文献です