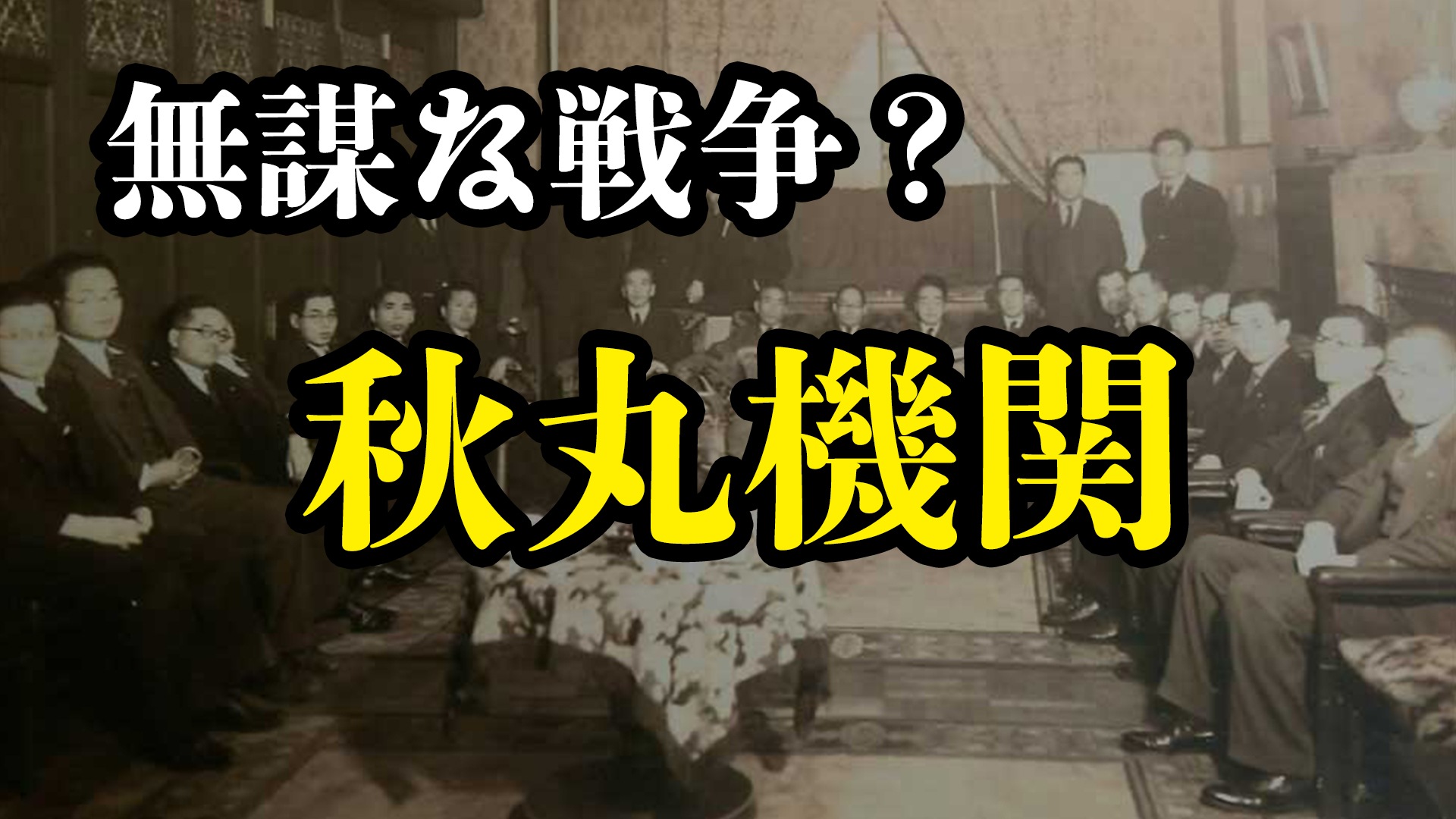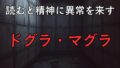戦後80年所感と「秋丸機関」の実像
石破茂元首相は「戦後80年所感」の中で、
なぜ日本は避けられたはずの戦争に突き進んだのか に触れた。
陸軍省が設置した「秋丸機関」の予測によれば、敗戦は必然であり、
多くの識者も戦争遂行の困難さを感じていました。
政府および軍部の首脳陣もそれを認識しながら、
どうして戦争を回避するという決断ができないまま、
無謀な戦争に突き進み、
国内外の多くの無辜(むこ)の命を犠牲とする結果となってしまったのか。
秋丸機関とは?
- 正式名称: 陸軍省戦争経済研究班
- 活動期間: 1939年秋〜1941年7月
- 目的: 米英独日など主要国の経済力を分析し、日本が戦争に入った場合の国力・兵站を予測
- 報告先: 陸軍省・参謀本部の首脳部
時代背景
- ドイツがポーランドに侵攻し第二次世界大戦が勃発
- 日本は満州事変・国際連盟脱退・日中戦争で孤立
- 米英との関係は急速に悪化し経済的に依存度が高かった
組織とメンバー
- 秋丸次郎中佐が率いる
- 東京大学の経済学者・統計学者・官僚など 約100〜200名 の大規模組織
- 治安維持法違反で検挙されていた有沢広巳(東大助教授)も中心メンバー
- 有沢には破格の月給500円(平均管理職75円)
- 9,000種以上の機密資料を収集し、班ごとに研究:
- 英米班
- ドイツ・イタリア班
- ソ連班
- 日本班
- 国際政治班
秋丸機関の主要分析
1. 日本の脆弱性
- 資源が少ない「持たざる国」
- 輸入の81%が英米依存、特に52%がアメリカ
- 生産力はすでに限界で、南方資源に依存せざるを得ない
2. ドイツの限界
- 1941年時点で経済抗戦力は限界
- 食料はウクライナ依存、石油はソ連領へ依存
- だからドイツはソ連に侵攻した(バルバロッサ作戦)
3. 英米の圧倒的国力
- 英米の戦争遂行能力は日本の20倍
- 英米の想定戦費は各800億円(米国は結局1.4兆円)
- アメリカの生産設備は20~25%が遊休 → 伸びしろ大
- 兵力動員の想定:250万人(実際は1,600万人)
アメリカの造船力と予想外の伸び
- 英米の造船能力は年間600万総トンと予測
- 実際はブロック建造方式で 1,250万総トン(予測の2倍)
- 溶接技術の進歩で大量生産が可能
- ドイツのUボートによる撃沈を圧倒的生産力で上回った
秋丸機関の結論
- 最大抗戦力の対象はアメリカではなくイギリス
- 英米は戦争準備に1〜1.5年かかる → その間に英国を弱体化
- インド洋の交通路遮断でイギリスを経済的に追い詰めるべき
実際の戦争とのズレ
- 秋丸機関は「対米直接戦争」を想定していない
- しかし日本は真珠湾を攻撃 → 対アメリカとの構図となる
- ミッドウェー海戦の敗北により戦局が一変
- 秋丸機関のシナリオとは大きく異なる展開に
資料の焼却と残された謎
- 戦後、有沢広巳が「秋丸次郎からすべて焼却するよう命じられた」と証言
- しかし後に一部の資料が発見される
- 報告書が政策にどれほど影響したかは不明
- 現在も多くの謎が残る
最後に
戦争シミュレーションの数字の裏には、必ず多くの命がある。
国が研究報告をどう受け止め判断するかが歴史を大きく左右する。

おが太郎
今回の参考文献です