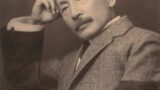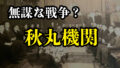人間はある目的をもって、生まれたものではなかった。これと反対に、生まれた人間に、初めてある目的ができて来るのであった。
最初から客観的にある目的をこしらえて、それを人間に付着するのは、その人間の自由な活動を、すでに生まれる時に奪ったと同じことになる。
だから人間の目的は、生まれた本人が本人自身につくったものでなければならない。

夏目漱石『それから』の有名な一説です。
「自分が生きている目的は何なんだろうと、誰しも一度は悩むと思います。
そして、その答えはなかなか見つかるものではありません。
それでも自分で考えて、行動して自力で見つけ出すしかないのです。」
漱石はこのように考えていたようです。
幼少期~学生時代
1867年に誕生、夏目金之助が本名
父親は町名主(町内をしきる役人)
→しかし、明治に町名主が廃止されたため、没落していった
漱石は8番目の子供であった(父親は51歳、母は41歳の時の子供)
家庭の困窮やお乳が出なかったことから里子に出されることになった
その後実家に戻ってくるも、すぐに塩原家に養子に出された(このとき1歳)
しかし養子に出された先の夫婦が9歳の時に離婚したため、夏目家に戻ってくることになった
このとき本当の父母のことは祖父母と聞かされていた

後の話ですが、お手伝いさんから本当の父母については知らされることになります。
そのせいもあって一家の人間はどこかよそよそしさはあったと言われる
唯一漱石に対して優しかった母も14歳の時に病気で亡くなってしまう
その後漱石は通っていた中学を辞め、漢学の塾に入ることにした
漱石は漢学のような中国の古典が好きだったためである
しかし入った塾は江戸時代の寺子屋のようなもので、
講義も昔の人が言ったことの繰り返しばかりで新しい考えはなかった
古臭い学問をこのまま続けいていたら「このままでは時代に取り残されてしまう」と感じ、
せっかく入った塾を辞めてしまう。
この頃から漱石は文学に興味を示すようになる
しかし一方で時代の波にのまれまいとしたかったため洋学を学ぶ
持っていた漢学の本は全て売り払ってしまった
英語が好きでだったわけではないが一生懸命勉強して、東京大学予備門予科に入学することができた
神田に下宿することになったが、同じ予備門の学生はバンカラばかりであった。
漱石もそのような連中と遊びまわったため落第することになる。
素行が悪かったため追試を受けさせてもらえなかったことにショックを受け、
人の信用を得ることは大事であることを学んだとされる。
その後はずっと首席の成績を修めることになる
ちょうどこの頃夏目家は長男・次男が病気で亡くなり、家を継ぐ男は三男と漱石だけになった。
しかし三男がとても頼りなかったため父親はこの頃から漱石に目を向けるようになった。
姓も夏目となり、夏目金之助となった。

それまでは塩原金之助だったんですね。塩原家に養子に出されていたままの状態・・・
思い悩みの多かった青年期
東大予備門の本科に進学する際に、専攻を決める必要があった
そこで漱石は建築科にしようと考えていた。

漱石は「自分の性格は強情でへそ曲がりで他人に頭を下げたくない、だから建築のような世の中に必要な仕事であれば向こうから頭を下げてくるに違いない」と考えて建築科を志望したようです。
しかし友人の米山保三郎がその漱石の考えを否定した。
「漱石がいくら頑張ったところで今の日本でセントポール寺院のような名建築を後世に残すことは無理だ。それよりも文学をやれ。文学には永遠の生命がある。数百年、数千年も読み継がれる大傑作も夢ではないじゃないか」
この米山の話を聞いて、食いっぱぐれたくないだけで建築を志そうとした自分が恥ずかしくなり、
文学家を志そうと決意し、英文科を専攻することにした。
本科を卒業し、23歳の時に東京帝国大学英文科に入学することになる。
★正岡子規
漱石に影響を与えたとされる人物で有名なのが正岡子規である。
子規とは寄席好きで共通の友人となった
お互いがそれぞれ書いた作品を批評しあうなどして交友を深めた
ちなみに学業の成績は正反対であった
漱石はいつも子規に勉強を教えていたと言われている
漱石はその後東京帝国大学を卒業して英語の講師となった。
正岡子規の故郷である松山で働くことになった。

一時的に正岡子規と同じ下宿先で同居していたようです。仲いいですよね。
ちょうどそのころ中根鏡子とお見合いをした。
その後熊本に引っ越し結婚する。
最初の子供は流産し妻の鏡子が精神的におかしくなってしまうこともあった。
しかしその後は無事に長女が生まれることになる。
プライベートは紆余曲折していたが、仕事は順調で教授になることができた。
しかし自分が本当にやりたいことについて思い悩むようになる。

文学がやりたいのに講師職ですからね・・・
イギリス留学へ
そんな中文部省から英語研究のためにイギリス留学を命じる通達が届いた。
漱石はいろいろ悩んだが現状を打開したい想いがあり、イギリスに留学することにした。
パリ万博の見物をしたあとロンドンへ向かう。
ちょうどその頃のイギリスはビクトリア女王治世下の最盛期であり、教育や経済、科学技術などの発達がめざましかった。その繁栄の象徴が首都ロンドンであった。
ロンドンでの生活は大変でかなり貧しい生活をしていた。
加えて勉強も思うようにはかどらずに心身をすり減らしていた。
世界一の都市ロンドンの発展の裏にはロンドンの影の部分も多く見られた。

イギリス留学中に親友の正岡子規は亡くなっています。漱石は手紙で知ることになります。
約2年間の留学を終え、家に帰ってくると寂れていた。
鏡子の父親が株に手を出して失敗し、家が傾いていたためである。
まずは家をどうにかしないといけなかったので、東京に引っ越し東京帝国大学の講師として就職した。
しかしその選択がさらに自分を追い込むことになる。
やりたくもない講師の仕事をして、本当にやりたい文学には手を出せていない。
そのことがさらに漱石の神経をすり減らすことになっていた。
鏡子にもかなりつらく当たったりし、実家に帰らせたりしてしまった。
しかし鏡子はそれとなく医者に診断させ、漱石の躁鬱状態が精神的な病であることがわかり、鏡子は腹を決め、漱石のもとにいることにした。
作家夏目漱石の誕生
そんな中、漱石の家に一匹の猫が住み着いた。
この猫の特徴が真っ黒で福猫であったため(当時は黒が福猫であった)飼われるようになった。
このころの漱石は大学の講師としては大人気となり、また明治大学でも講師職を得ることができ、お金も潤うことになった。
しかし精神的な病は治らず、見かねた鏡子は門下生たちに頼んで無理やり家の外に引っ張り出してもらうようにしていた。
その中の一人高浜虚子が雑誌に載せるための何か文章書いてほしいと漱石にお願いをした。
その漱石が書いた文章の出だしがあの有名な「吾輩は猫である。名前はまだ無い」であった
この文章の題名がまだ決まっていなく、『猫伝』にしようかと悩んでいたが、虚子が「書き出しの部分の方がいいでしょう」と言ったため、あの名作『吾輩は猫である』が生まれることとなった。
そしてこの小説は俳句雑誌「ホトトギス」に掲載される。
この時の自分の名前に夏目漱石と使った。(以後死ぬまでこの名前を使うことになる)
つまり『吾輩は猫である』は夏目漱石の誕生となった記念すべき作品であり、漱石の小説家としての華々しいスタートを飾ったものであった。
この『吾輩は猫である』は驚くほど好調な売れ行きをたたき出したため、原稿料や印税で夏目家の家計はかなり潤うことになった。まさに家に住み着いた猫は福猫であった。
★漱石の名前の由来
・「枕石漱流(ちんせきそうりゅう)」石を枕に流れに漱(くちすす)ぐ
・「枕流漱石」(ちんりゅうそうせき)流れに枕し、石に漱ぐ
枕石漱流を枕流漱石と誤って言ってしまった人がいた。
しかし流れに枕するのは耳を洗うためであり、石に漱ぐのは歯を磨くためである負け惜しみを言った
←頑固で意地っ張りな自分にぴったりと思い「漱石」と名付けたのが由来。
小説家としての成功
その後『坊ちゃん』や『草枕』を執筆した。
どちらも雑誌が売り切れるほどの人気作となり、世間は漱石を人気作家としてもてはやした。
そして文学に対する決意が固まり漱石は40歳にして講師を辞め、新聞社専属の作家として転職をした。
「とにかくやめたきは教師、やりたきは創作」
大学の講師職の方が世間的には上であったため、様々な批判も巻き起こった。
そんな中で新聞社勤めとして出した作品が『虞美人草』である。
皆が注目する作品となってプレッシャーもあったが、そのプレッシャーを押しのけるかのごとく人気作となった。
その後立て続けに『坑夫』や『夢十夜』『三四郎』を出す。

この『三四郎』執筆の間に住み着いていた福猫が亡くなっています。結局名前はもらえなかったんですよね。
作家として成功を収めた漱石のもとには多くの門下生が集まった。
漱石は若い作家たちにも「朝日」の紙面を提供して作品を書かせるなど割と面倒見も良かった。
漱石のイメージは世間的には謹厳実直な強面のような印象だが、実際は情に厚い面もあり、調子に乗ると皮肉やダジャレを言ったりするような人物であったと弟子が後々語っている。
いわゆる漱石三部作と呼ばれる『三四郎』に続き『それから』と『門』を出す。

ちなみに『門』は続編を早く世に知らしめたい出版社に対して漱石の門下生が適当につけた題名です。物語に門が全く関係ないままストーリーが進行して紙面担当がやきもきしたエピソードもあるくらいです。
漱石の小説全般に言えるかもですが、タイトルは適当につけている印象がありますね・・・
病気との闘い
『門』の執筆が終わったころ、漱石は大量の喀血をする。
そして一時的ではあるが危篤状態になってしまった。
何とか一命は取り留めることになるも人生について色々と考えることが多くなった。

ちょうどこの頃に文部省から文学博士号を授与する通知が来ますが断ってしまいました。
「いらないものはいらない」
上から押しつけてくる権威が嫌いであったようですね。
またこの頃に生まれて間もない五女を亡くしてしまう悲劇に見舞われ、精神的にもかなりどん底状態となってしまう。
胃潰瘍や痔の症状が悪化しながらも『彼岸過迄』『行人』『こころ』『道草』を執筆し発表する。

『こころ』は以前番組で扱ってます!ぜひ放送を聴いてください!
その後も毎年のように病気をしていたため、体もめっきり衰えていた。
門下生もそれぞれが独り立ちしていて、新たな顔ぶれに変わっていた。
その中の一人に芥川龍之介がいた。
1916年5月から連載の始まった『明暗』であったが、
その188回目の原稿を書き終えた漱石は189番目の原稿の上につっぷしていた。
そのまま床についたまま息を引き取った。49歳だった。
『明暗』は幻の未完成作品として、漱石死後も話題になった。
★漱石が芥川ら若手の門下生に伝えた言葉
「どうぞ偉くなってください。しかし、あせってはいけません。牛のようにずうずうしく進んでいくことが大事です。私たちはとかく馬になりたがるが、牛にはなかなかなり切れないのです。根気です。世の中は根気の前に頭を下げますが、火花は一瞬で忘れてしまうでしょう。牛のようにうんうん死ぬまで押すのです。何を押すのかと言うと人間を押すのです。」
夏目漱石の作品の特徴
新聞社に勤める形で作品を世に出していたため、新聞の連載小説がほとんどであった。
毎日不特定多数の読者相手に読んでもらえるものを書かないといけない。
難しい話や理屈っぽいものではなかなか新聞読者の興味を引くことができない。
そのためわかりやすさを重視されているものが多い。

漱石の小説は表現的に難しいものをわざと避けているような印象です。『吾輩は猫である』なんかは小学生でも読めると思います。(私も小5くらいで読んだ記憶ありますね・・・)
日常の出来事や人間関係のなかに、自分が抱え込んでいた様々な問題を描いた。
そのため同じような悩みを抱える人から共感を得ることができた。
晩年は「則天去私」の考えが作品にも強く表れていると言われる。(注:諸説あり)
「則天去私」とは天にのっとって私を去るという意味で、何事につけても自我を張らずにもっと大きな立場で物事を考えてみること。
→偉そうな理想や主義もくだらなく見えるし、くだらないと言われていることの中に大事なことが含まれていたりすることがわかる