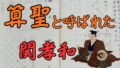謎多き女流絵師・葛飾応為(かつしかおうい)
高い評価を得ている江戸の女流絵師・葛飾応為。生まれた年も、亡くなった年も不明で、残る作品もごくわずか。だからこそ、その生涯は多くの謎に包まれています。
その謎に満ちた人生から、小説や映画にもなっています。
最近だと、映画『おーい、応為』(主演:長澤まさみ)などがあります。
本名と由来
応為の本名は「お栄」。父・北斎は、最初のうちは「お栄」と呼んでいましたが、だんだんと「おーい」とだけ呼ぶようになり、それがそのまま「応為」という画号になったといわれています。
生い立ち
応為は葛飾北斎の三女として生まれました。生年は不明ですが、1800年ごろと推定されています。北斎は二度結婚しており、応為は後妻・ことの子。幼いころから父のそばで絵を学んだと考えられています。
初期の作品『大海原に帆掛け船図』
14歳のころに描かれたとされるデビュー作で、「栄女筆」と署名。海に多数の帆掛け船を描き、遠近法を駆使して表現しています。すでにこの時点で西洋画の技法を取り入れていたことがわかります。
結婚と離縁
応為は絵師・南沢等明と結婚しましたが、結婚生活は長く続きませんでした。
- 夫の絵を「下手だ」と笑ってしまい離縁された
- 自由奔放な性格で、家事をせず、男勝りだった
離縁後は再び北斎のもとに戻り、親子で「ゴミ屋敷」のような家で暮らしたと伝えられます。掃除や洗濯をせず、家が汚れると近所の空き家に引っ越したという逸話も残っています。
父・北斎との関係
応為は「顎が出ていて美人ではなかった」と伝えられ、北斎は「アゴ」と呼び、応為は「何だい親父殿」と返したそうです。しかし、その性格は義理人情に厚く、父の晩年を支え続けました。
画風と才能
北斎は「余の美人画は阿栄に及ばざるなり」と語っており、応為の美人画の才能を高く評価していました。
代表作
『吉原格子先之図』
江戸の遊郭・吉原の張見世を描いた浮世絵。光と陰の表現が見事で、「江戸のレンブラント」と呼ばれるほどの陰影技法が使われています。
この作品は長く行方不明でしたが、1982年に再発見され、再び注目を浴びました。提灯に隠し落款「應・為・栄」が仕込まれており、応為の作とされています。
『夜桜美人図』
星空の下、若い女性が灯籠の明かりで短冊を書く様子を描いた名作。3つの光源(石灯籠・雪見灯籠・星空)を使い分け、日本で初めて夜の色調変化を描いた作品とされています。
女性は実在の歌人・秋色(しゅうしき)とされ、応為の「酔女」の署名に通じる洒落が込められています。
艶本(えんぽん)
男女の情交を描いた艶本『つひの雛形』。長らく北斎の作とされてきましたが、隠し落款「栄」が見つかり、応為の作ではないかとされています。
江戸時代に艶本を描いた唯一の女性絵師ともいわれています。
応為の特徴
- 光と陰の表現 ― 西洋的な陰影法を駆使。
- 女性の指先 ― 関節まで丁寧に描写し、繊細さを表現。
- ほつれ髪の描写 ― 耳元の髪がくるんと跳ねる自然な仕草。
これらの特徴により、署名のない作品の中にも応為の手が入っている可能性が高いとされています。
晩年の北斎と応為
北斎は90歳まで生きましたが、晩年の色鮮やかな作品には応為が関わっていたと考えられています。震える署名や細部の仕上げから、応為が実際に筆をとっていた可能性も指摘されています。
北斎の死後、応為は仏門に入り、約67歳で亡くなったといわれています。
北斎と応為の比較
| 項目 | 葛飾北斎 | 葛飾応為 |
|---|---|---|
| 特徴 | 構図と遠近法に優れる | 光と陰の表現に秀でる |
| 描写 | ダイナミックで大胆 | 細部まで緻密で繊細 |
| 評価 | 世界的巨匠 | 近年再評価される |
おわりに
応為は、父・北斎に劣らぬ才能を持ちながら、時代の影に埋もれて生涯を終えました。
しかし、現代の研究により、その革新的な「光と影」の表現が再び注目を集めています。
女性が画家として名を上げるのが難しかった江戸時代に、己の感性を貫いた女流絵師・応為。
その作品は今もなお、静かに光を放ち続けています。