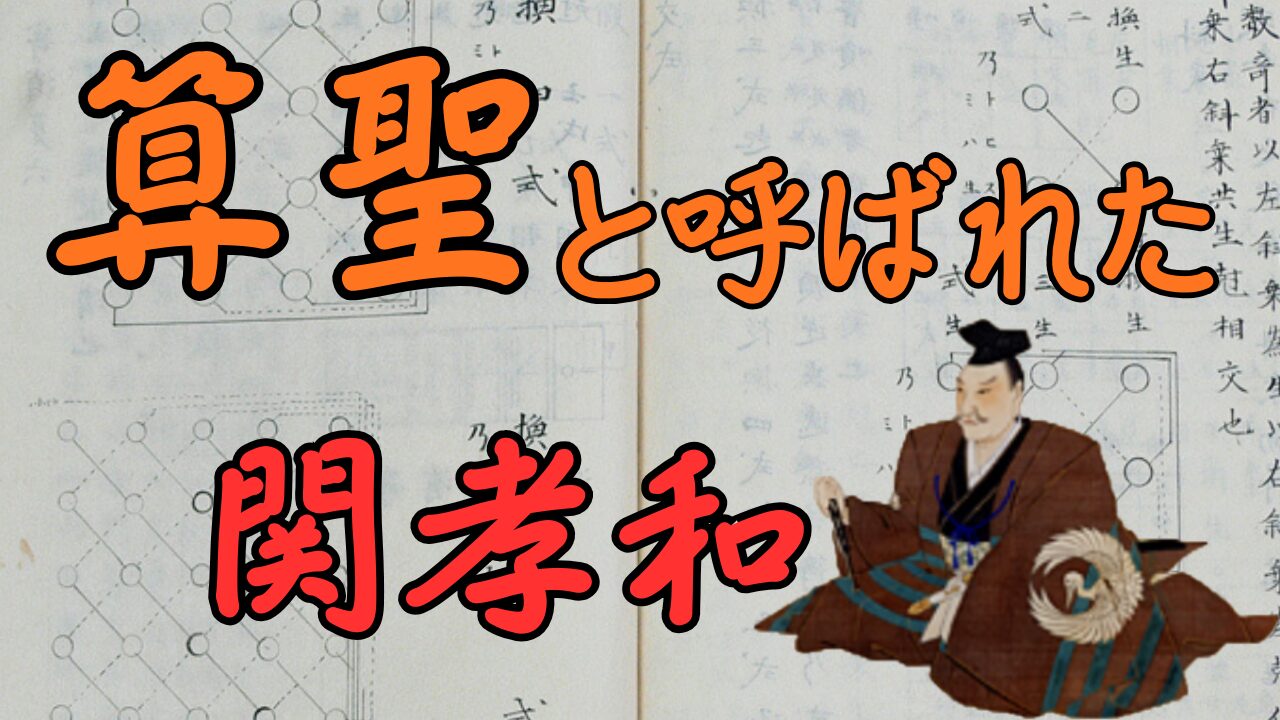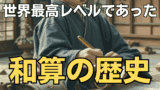「数学の世界というのは自分で自分の道を、自由な発想で切り開いていけるのです」
★参考文献
関孝和の生涯

関孝和は和算を飛躍的に発展させた最重要人物として登場するのですが、史料の乏しさゆえ不明な点も多い人物です。今回は学術的に一般的に認められている範囲でお話してますが、一部仮設も含んでしまってるかもしれない点ご了承ください・・・
関孝和は、江戸時代前期の17世紀半ばに生まれた日本の数学者
★正確な生没年は不明
(おそらく1640年頃に生まれ、1708年に亡くなったとされる)
生まれた場所も正確には不明であり、藤岡か江戸のどちらかと言われる。
江戸時代になると和算と呼ばれる日本独自の数学が広まった

和算が広まった背景については和算の回をご参照ください
関孝和は、武士の家に生まれた
武士としての教育の中には、儒学・兵法・書・算などがありましたが、
彼は特に「算術(和算)」に強い関心を示した
逆に言えば儒学や武芸はあまり好きではなかったとも言われている
後年発見された書物からは独学で『塵劫記』を読み、数学を学んだともされている
関孝和の資料はほとんど残っていないため
どのような仕事をしていたのかも明確に言えるものは少ない
勘定役(現在の財務・経理担当官)に相当する役職勤めであったとされる。
関孝和の業績

そんな関孝和はどんな業績を残したのか?
たくさんありすぎるのですが、大きく分けて4つにしました。
(数学の専門家でないのでカテゴリ分けが怪しいところありますがご容赦ください・・・)
天元術の発展
天元術とは、未知数を「天元」と呼ばれる記号で表し、多項式方程式を立てて解く手法である。
中国の「天元術」はすでに宋代に存在していたが、関孝和はこれをさらに一般化・精密化した。
関孝和は代数学的な思考法を導入した最初期の人物とされる。
未知数を文字で表して方程式を立て、計算で未知数を求めるという近代的な代数の基礎を築いた。
傍書法と呼ばれる独自の記号法で天元術を格段に飛躍させた。
また、関の数学書『発微算法(はつびさんぽう)』(1674年刊)は、和算史上の金字塔的重要な著作であり、後世の和算家に強い影響を与えた。

『発微算法』は超難問と言われた『古今算法記』の偉題を解いたことで有名な書です。
行列式の先駆的研究
行列式とは数を縦横に並べた行列に対する計算方法(展開式)で、
孝和はこれをふたつの変数を含む二つの方程式から、未知数を消去する過程で発見したいわれている。
これは西洋数学よりも約10年早い発見であった。
なお西洋数学では、行列式はライプニッツが1693年に導入したのが最初だった。
のちに孝和の解法は3次の行列式までは正しかったが、4次以上には誤りがあることが判明した。
円周率を小数点以下11桁目まで求めた
円周率とは・・・円の円周の長さと直径の長さの比率を表す
当時日本では円周率は3.16が使われていた
でも関孝和は感覚的に3.16よりは小さい気がしていた

円の長さが直径の3.16倍だと大きすぎる気がして糸とか使って長さを測ってたみたいです。
糸使っても正確に円周を測るのは困難ですし、大きいと言ってもほんの誤差くらいのものなのでよく気付いたなぁと感心します。
★関孝和が計算した円周率→3.14159265359
関孝和は円に内接する正多角形の周を計算して円周率に近づくという方法で上記を導いた
関孝和は正137032角形を使って小数点以下11桁まで計算することができた
この計算方法は現代では「加速法」と呼ばれるもので、世界に200年先駆けて発見したとされる
彼の弟子たち(特に建部賢弘)によってこの方向性はさらに発展し、
やがて「円理」の中で微積分的手法に到達する。
このように、関の研究は日本独自の数学的解析学の出発点を形成したと言える。
数表と算法の実用化
関孝和は理論家であると同時に、実用的な算術家でもあった。
彼は測量、年貢計算、土地割り、税務処理などに応用可能な算法を整備し、幕府の行政にも寄与した。
彼の計算方法は正確かつ体系的であり、当時の役人たちが利用する「算法便覧」としても重宝された。
また、関流という流派として弟子たちが関孝和の知見を発展させることで
18世紀から19世紀初頭にかけて和算界の主流となり、和算文化の黄金期を築くことになった
関孝和の評価
関孝和の数学は、当時の日本国内で極めて高い水準にあったが、
鎖国政策のために海外にはほとんど知られなかった。
そのため、ヨーロッパの数学史からは長らく独立して存在していた。
しかし、20世紀以降、数学史研究が進むにつれ、彼の業績は国際的にも注目されるようになった。
特に、関孝和の「行列式の発見」がクラメルやライプニッツより早い可能性、
また彼の「代数的思考」がデカルトやニュートンと同時代的である点が高く評価されている。
さらに、彼が体系化した和算教育は、江戸時代後期に至るまで全国に広まり、
日本人の数理的素養を大きく底上げすることとなった。
明治以降の理数教育の基盤にも、この和算文化が大きく寄与したとされる。

関孝和のいちばんの功績は、「計算のための算術」だった和算を、「理論を考える数学」に変えたことです。学問として体系的にしたことで、後進の数学教育の発展に寄与したと思います。それが現代の数学や科学につながる功績と言っても過言ではないかと個人的には感じています。