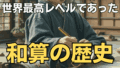冒険は最良の師 ― 榎本武揚の生涯と功績
「冒険は最良の師である」──これは、オランダ留学を経験した榎本武揚が友人に送ったオランダ語の言葉です。現在、東京農業大学(北海道)に飾られています。彼は東京農業大学の前身である育英黌(こう)農業科の設立にも関わりました。
1. 幕末の青年・榎本武揚の生い立ち
1836年、幕府旗本の次男として現在の東京都台東区に生まれる。父・円兵衛は幕府の天文方として徳川家に仕え、伊能忠敬の弟子として測量に従事。榎本も幼少期から朱子学やオランダ語を学び、中浜万次郎(ジョン万次郎)から英語も習得しました。
彼はオランダ語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、モンゴル語まで学ぶ語学の天才でした。19歳のとき、幕府の命で蝦夷地(北海道)・樺太の調査に従事し、海と北の大地に強い関心を抱くようになります。
2. オランダ留学と世界へのまなざし
1862年、幕府の選抜留学生としてオランダに渡航。航海術、蒸気機関学、鉱物学、電信技術、国際法など幅広い分野を学びました。
特に『万国海律全書』を通じて国際法を熱心に研究。理解を深めるために400時間以上を費やし、後の外交交渉に生かされます。また、留学中にデンマーク戦争を観戦し、クルップ砲の威力を学び、兵器技術にも関心を持ちました。
帰国後、幕府がオランダに発注した最新鋭軍艦「開陽丸」の艦長に任命されます。
3. 戊辰戦争と蝦夷共和国 ― 最後の武士として
幕府海軍副総裁となった榎本は、徳川慶喜の恭順後も旧幕府艦隊を率いて蝦夷地へ向かい、「蝦夷共和国」を樹立しました。ここでは日本初の選挙が行われ、榎本は156票を集めて総裁に選ばれました(2位は松平太郎の120票)。
しかし新政府軍との戦いに敗れ、五稜郭で自刃を試みるも部下に止められます。その後、2年半の牢獄生活に。獄中では科学技術や製造法を記録し、日本の未来のために知識を残しました。
4. 助命と再起 ― 黒田清隆との絆
榎本の命が助かった背景には、フランスの国際法書『万国海律全書』の存在がありました。榎本は自ら翻訳したその本を新政府に提出。黒田清隆は「彼ほど国際法を理解する者はいない」として助命を強く訴え、坊主頭にしてまで嘆願しました。
釈放後、榎本は黒田に信頼され、北海道開拓使に登用されます。彼は未開の地を自ら調査し、日本最大級の石狩の石炭山を発見。鉄道敷設を提言するなど、北海道開発に尽力しました。
5. 政治家としての歩み
明治政府では異例の旧幕臣として、逓信大臣、農商務大臣、文部大臣、外務大臣などを歴任。電信事業を国産化し、若手技術者の育成にも努めました。
また、1875年にロシアと「樺太・千島交換条約」を締結。樺太をロシア領とする代わりに千島列島全土を日本領とし、対等な外交交渉を成し遂げました。その後、シベリア横断の旅を行い、地質や動植物を調査。科学者としての探究心を最後まで失いませんでした。
6. 晩年と流星刀
晩年、榎本は富山県で発見された隕石を購入し、これを素材に「流星刀」と呼ばれる刀剣5振りを製作。そのうち4振りが現存し、世界でも極めて貴重な刀とされています。
1908年、72歳で病没。学者・外交官・開拓者・政治家として、多彩な足跡を残しました。
「冒険は最良の師である」―― 榎本武揚の生涯は、まさにこの言葉を体現したものでした。