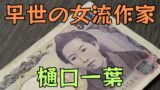「この話は、読んでしまって知っている。だけど、もう一度読みたい。」
by 俵万智
樋口一葉について
1872年生まれの明治時代の女性作家
わずか24年という短い生涯ながら、多くの名作を残し、日本近代文学に大きな足跡を残しました。
生活苦の中で筆を執り、下町に暮らす庶民や女性の繊細な感情を細やかに描き出したことで知られています。
特に少女から大人へ移ろう心の揺らぎや、社会の矛盾に翻弄される女性像は、今日でも高く評価されています。
彼女の作品は写実性と抒情性が融合し、近代文学の先駆けとしての位置を占めています。

詳しくはこちら
★奇跡の14か月
亡くなる1年前の約14か月間に多くの名作を執筆しており
『たけくらべ』もその間に発表したものです
『たけくらべ』あらすじ
<登場人物>
美登里
→14歳、近所の子供たちのガキ大将的存在
気前が良く勝気な性格
信如
→僧侶を父に持つ15歳の少年。
真面目で内向的な性格。
正太郎
→13歳、金貸しの息子。
喧嘩っぱやく、美登里のことを慕っている。

今で言う中学生くらいの子供たちを主役に描かれています。
<あらすじ>
吉原に住む14歳の勝気でおてんばな少女美登利は遊女の姉を持ち、
自身もゆくゆくは遊女となることが決まっている。
弟分のような存在の正太郎という少年とよく遊んでいた美登利だが、
心の中では寺の息子である信如のことが気になっていた。
運動会の日、木の根につまずいた信如に美登利がハンカチを差し出したところ、
他の生徒たちから冷やかされてしまう。
変な噂が立つことを嫌った信如は美登利を無視するようになり、
悲しく思った美登利も信如に対して冷たい態度を取るようになった。
ある雨の日、信如は美登利の家の前で下駄が壊れて困っていた。
美登利は身を隠して補修用の布切れを投げてやったが、
信如は恥ずかしさからその好意を無視してしまう。
そんな中、美登利は頭を島田髪に変えられる。
これは、彼女が大人になり吉原の遊女となる日が近づいていることを意味した。
美しく着飾った美登利に正太郎が声をかけるが、
彼女は悲しげな様子で「大人になることは嫌なこと、なぜこのように歳を取ってしまうの…」と、
彼を拒絶する。
それ以降、美登利は他の子供とも遊ばなくなり、引きこもりがちになる。
ある朝、美登利の家の門に水仙の造花が差し込まれていた。
これを見て彼女はなぜだか懐かしく、少し物寂しい気分になり、それを部屋に飾る。
後になって分かったことだが、
それは信如が僧侶の学校に入るために吉原を旅立つ前日のことだった。
解説
<たけくらべのタイトルについて>
よく勘違いされるのは「竹」くらべ
竹取物語的な連想から勘違いされやすい
たけ→「丈」くらべ→背丈の意味合い

中学生くらいの少年少女の物語なので、背丈の意味合いが強いと思われます
<作品を良く言えば・・・>
一葉作品全般に言えるがリズミカルな文体
また、柔らかい言葉遣いが特徴
一葉自信が和歌を習練していたので、それを活かした独特なセンスが際立っている
<作品を悪く言えば・・・>
話中に出てくる言葉(表現)が難しい
会話の区切りがわからない
文語体で書かれているため、現代人には馴染みにくい
<内容について>
物語全体が問いになっていて、答えがないまま、ふわっと終わっている
美登里がこれからどうなるのかはわからない
水仙の造花を差し入れたのが信如なのかもわからない
→そもそも何で造花なの?という疑問もある
2人がもう結ばれることはないのかもわからない
→ただ二人の道は正反対の道であり、それが再び交わることはおそらくない
<作品について>
一葉作品は一度読んでぴんとこなかったとしても、騙されたと思ってもう一度読んでみてほしい。
それで良さがわかるのが特徴的でもある。

私も初見は全くわからなかったのですが、2回目でスッと良さがわかる場面が多かったです。
★ながまろオススメの読み方
まず現代語訳を読んでストーリーをある程度理解してから、原文を読むと良いかも
そうすることで一葉の表現であったり描写力のすごさに気付くことが多いと思う
参考図書~青空文庫より~