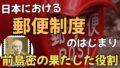髪は時代とともに女性の美を象徴し続けてきました。その歴史をたどってみましょう。
女性の黒髪の歴史
明治の断髪令と女性への規制
1871年、政府は散髪脱刀令(通称:断髪令)を発布。男性の髷を廃止し、刀を差す習慣をやめることを推奨しました。
規定には男女の区別がなく、女性の中にも断髪を行う人が現れましたが、それに対して厳しい批判が巻き起こります。
翌年、東京府は女性の断髪禁止令を発布。違反者には賠償金や拘留の罰則まで課されました。新聞や雑誌も「断髪は男性に限られるべき」「女性は従来通りの髷を守るべき」と伝えています。
なぜこれほどまでに女性の断髪が批判されたのか?
それは世界共通で女性の髪は長く保たれる傾向があり、長い髪が「女性らしさ」の象徴、さらにはセックスアピールや保護的欲求を引き出す要素と見なされていたからです。
平安時代 ― 長く艶やかな黒髪の美
平安時代、女性の髪は長ければ長いほど美しいとされ、文学には6尺(180cm)以上、時には7尺(210cm)もの長髪が描かれました。
「髪の長きは七難隠す」ということわざの通り、髪の美しさは他の欠点を覆い隠すほどの価値を持っていたのです。
ただ長いだけではなく、艶やかな黒色こそが理想でした。日本の伝統色には「漆黒」「紫黒」「黒鳶」など多彩な「黒」が存在し、日本人の黒への繊細な美意識は女性の黒髪にも強く反映されました。
長くて艶やかな黒髪は、美人の象徴であると同時に、
労働をせずに済む、社会的地位の高さを示すシンボルでもありました。
そのため、髪を洗う作業も一日がかり。米のとぎ汁や植物の灰汁を使い、乾燥にも半日以上を要しました。美しい黒髪を保つことは、上流階級女性だけが持てる特権だったのです。
庶民と髪型の違い
労働に従事する庶民の女性には長髪は不便でした。彼女たちは髪を短く切るか結い上げ、実用的な髪型をしていました。
一方、上流階級では髪を結わずに垂らす垂髪(すいはつ)が好まれ、美人の象徴とされました。
垂髪は顔を隠す役割を持ち、顔を見せない恥じらいこそが美とされたのです。扇や袖で顔を隠す所作と同じく、「見せない」ことが初々しさや可憐さを表現していました。
髷(まげ)の発展と美意識
室町から江戸時代にかけて、垂髪は次第に廃れ、武家や庶民を中心に結髪(けっぱつ)が広まります。そこから多彩な髷(まげ)が発展しました。
髷には武家風・町方風、京風・江戸風、未婚・既婚などのバリエーションがあり、その形を見るだけで女性の身分や立場が分かるほどでした。
髪を固めるには胡麻油や胡桃油、庶民は動物性油を用いることもあり、宣教師ルイス・フロイスは「悪臭を放つ」と記しています。
さらに髪油が襟に付くことを避けるためにうなじが露出し、やがて「うなじ」そのものが美の象徴へと昇華していきます。
明治時代 ― 西洋化と束髪の広まり
明治維新後、西洋文化の流入とともに髪型も変化します。
政府の断髪令は本来男性を対象としていましたが、一部女性の断髪は社会的非難を浴びました。
その一方で、外交場として建てられた鹿鳴館で舞踏会が開かれると、日本女性も洋装に合わせた夜会巻きを取り入れるようになります。
1885年には婦人束髪会が結成され、「日本髪を廃止し束髪を普及させる運動」が広がります。
ただし、世間にはなかなか受け入れられず、断髪や束髪は「夫婦の離縁」にまで発展した事件(1887年・朝日新聞掲載)もありました。
やがて束髪は定着し、日本髪=伝統、束髪=新しい女性像という二分化が生まれます。
大正・昭和 ― 新しい流行と断髪
大正期には洋風のウェーブヘアが流行し、耳を隠す髪型や断髪が女性たちの間で広がります。第一次世界大戦では「祖国のために髪を切った女性」が象徴的な存在となりました。
戦中はおかっぱや銃後髷など、衛生的で実用的な髪型が推奨され、戦後はショートカットが流行します。
1954年には映画『ローマの休日』の影響でヘップバーンカットが一世を風靡。その後は聖子ちゃんカット、ギャルの盛り髪など、流行は短い周期で変化を繰り返しました。
まとめ ― 髪型に込められた女性の美意識
髪型の歴史を振り返ると、社会の支配層が変わる時に大きな転換がありました。
公家から武家、江戸幕府から明治政府、戦後のGHQ統治…。その度に女性の髪型も大きく変化しています。
しかし、どんな時代も共通していたのは、「美しくなりたい」「可愛くなりたい」という女性の欲求なのかもしれない。