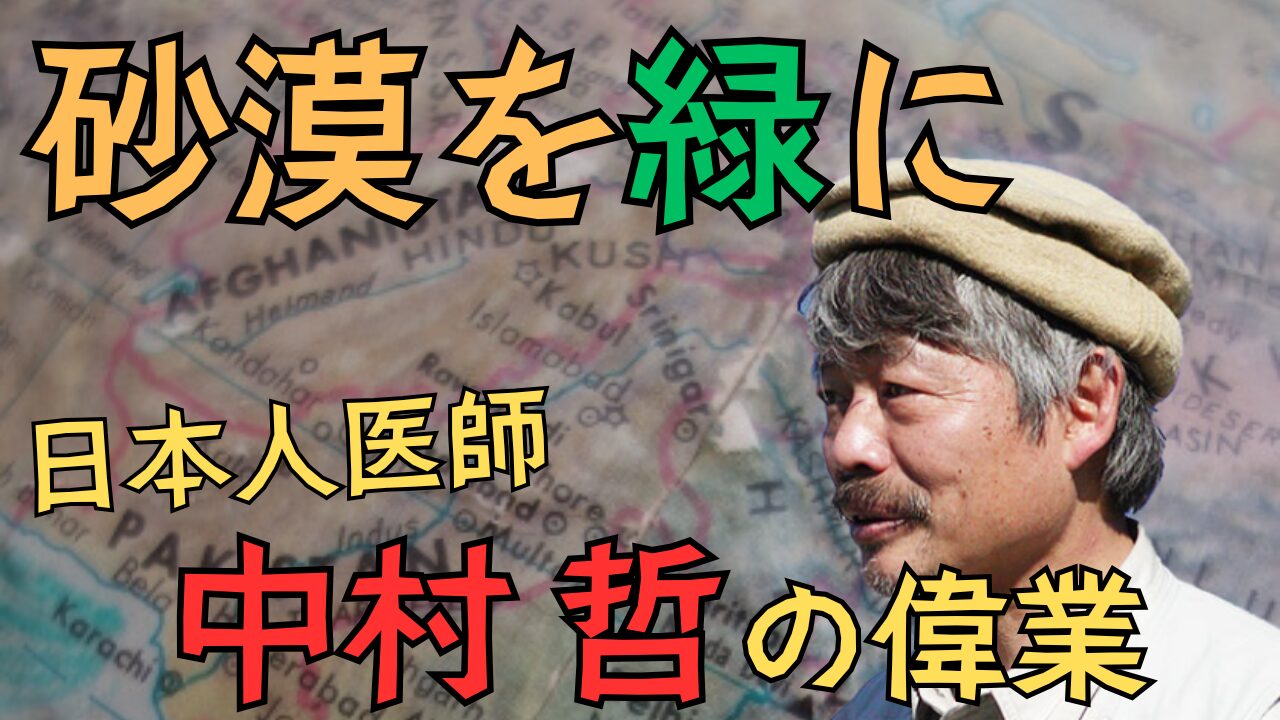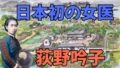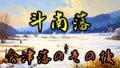「金が無くても食っていけるが、雪が無くては食っていけない」
アフガニスタンのことわざです。
降水量が少ないアフガニスタンでは雪解け水がとても重要な水源となっています。
背景
2000年の春にユーラシア大陸中部は史上最大規模の干ばつにさらされた
この干ばつの被害が最も大きかったのがアフガニスタンと言われている
★WHOの発表
人口の半数以上が被災しており
400万人が飢餓の危機にあり、
100万人以上が餓死の危機に瀕している
※アフガニスタンの人口は4000万弱
実際にアフガニスタンは食糧生産が半分以下となった
また、家畜の9割が死んでしまった
人々はこの大干ばつに苦しめられることになった
中村哲について
1946年福岡県生まれ
小さい頃は虫が好きだった
昆虫観察をよくしており、そのため物事を観察する習慣が身に付いた
また、祖母がとても厳しい人であった
その祖母から「弱いものはすすんでかばうこと」を教えられた
このような幼少期の教えが将来の活動へつながっていくことになる
哲の住んでいた地域は医療過疎の問題が起きつつあったため
人のためになることをしたいと思っていた哲は医者を目指すことになる
そして医者になったが、当時の医療界はとにかく長生きさせることが大事の考えであり、
呼吸ができない患者には人工呼吸器をつけて1秒でも長く生きてもらうことを求めていた。
「医療は壊れた道具をただ直すようなことであってはいけない」
哲はどう生きるかについて深く考え自問自答していくことになる
そんな中、海外登山隊に同行する医師を募集しており、
哲は喜んでその仕事を引き受けることになる
小さいころから昆虫採集のため山に行っていたりしたし、
珍しい昆虫など見られると思ったということもある。
そして派遣された場所がヒンドゥークシュ山脈(パキスタンとアフガニスタンの間)
そこで悲惨な現地の状況を目の当たりにする
多くの住民が医師が不足している中、治るはずの病気で苦しんでいる
特にハンセン病患者が目立っていたとのこと。
パキスタンのハンセン病患者は約2万
それに対してハンセン病を診れる医者の数はたったの3人
哲はハンセン病患者を治療するための活動を行っていくため、パキスタンに診療所を開設

とは言っても先進国の医療をそのまま取り入れたわけではなく、劣悪な環境からのスタートだったそうです。
現地には治療に必要なものは全くそろっていなかったらしく、
2400名の患者に対して入院できるベッドはたったの16台だけ。
医療器具を乗せるカートは1台のみ(しかも壊れている)
ねじれたピンセット、耳にはめるとケガをしてしまう聴診器
ガーゼも使いまわしするしかないような悲惨な状態であったそうです。
苦難を乗り越え哲は多くのハンセン病患者を治療した
その後アフガニスタンへ移動し、アフガニスタンでも診療所を開設し活動していく。
乾いた砂漠に緑を~井戸作りと用水路建設~
人は水がないと数日も生きられない
「もう病気の治療どころではない。とにかく水が必要だ。」
村人が使っていた井戸はすっかり干上がっていた
畑はひび割れ石がごろごろ転がっている
わずかに水が出る井戸に人々が殺到し殴り合いが起きていた
哲は村人を集めてツルハシやシャベルでの手作業で深い井戸を掘り始めた
しかし大きな石にあたってしまうとツルハシでもどうにもできない
そのため日本から井戸掘りの専門家を呼んだ
その土地にある技術でやれる限り井戸掘りすることを鉄則とした
大きな石は掘削機で穴をあけて爆薬で細かく粉砕した
←爆薬はアフガニスタンのソ連侵攻時の不発弾などが当てられた
このような活動を繰り返すことで2001年9月までには660か所も作り
そのうち90パーセントで水を出すことができた
しかし井戸では飲料水が確保できても農地を潤す水とはならない
そこで伝統的な灌漑用水路(カレーズ、カナート)を復旧させることにした。
井戸の底を横につなぐ穴を掘った。
その結果砂漠化した田畑が短期間でよみがえった。
約30万人もの人が農業を続けられるようになった。
しかしそれでも水はドンドン枯れてきてしまった。
そのためクナール川から水を引く本格的な用水路を建設することにする。
しかし哲は土木工事においては素人である。
自分の娘の高校数学の教科書を借りて土木工学の勉強からスタートした。
また、用水路を造るにしても日本の技術をそのまま取り入れなかった。
現地にあるもので作り、現地人がメンテナンスできるようにした。
アフガニスタンと日本の川は実は似ていた。
傾斜地が多く川の流れが速く、季節による水位差もあり、山間の平野部で農業をしている
石が多いので割った石を積み上げ石垣を造った
その両脇には柳の木を植えた
☞こうすることで根が石の間に入り込み強度が強くなる
川へつなぐ道をただ掘っただけでは水は上手く流れない
取水口の問題が最難関だった
強い流れの川から水を引き込むのは大変。
その参考になったのが故郷の筑後川であった。
筑後川から田畑に水を引くための山田堰を真似た。
山田堰は斜め堰といって川の流れの抵抗が少ない形に作られている

ちなみに山田堰は1790年に作られているものです。
苦難にあいながらも無事用水路は開通した
この用水路にはアーベ・マルワリード(真珠の水)と命名した
その後延伸や補修をいくつも行い、最終的には2010年に完成した。
死の谷ガンベリ砂漠まで水を通すことができた。
放送では言っていないこと
2001年アフガニスタンへのアメリカ侵攻が起きた際も大干ばつの影響を受けていた
哲は軍による侵略には大反対の立場を取っていたが、
当時の世論はタリバン=悪であり全く聞き入れてもらえなかった

多くの国民が飢餓に苦しんでいるときに侵略戦争を起こすなんて・・・
中村哲の最期
2019年12月4日
アフガニスタン東部のジャララバードを車で移動していた際に
銃撃を受け、乗っていた他5名の現地スタッフとともに亡くなった
この時向かっていた先も灌漑作業現場であった
哲を襲った武装集団はタリバン派の犯行とされている

様々な説はありますが、誘拐しようとして誤って殺害してしまったものと思われています。
哲は有名人であったので、何かの役に立つと思ったのかもしれません。
いずれにせよ許せない行為です。
多くのアフガニスタン人、パキスタン人が哲の訃報を聞き涙したとのことです。
しかし彼の功績は忘れ去られることなく今なお現地の人々の心に強く残っていることでしょう。