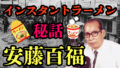「人その友のために、己の命をすつる、これより大いなる愛はなし」
生い立ち
1851年 誕生(埼玉県熊谷市俵瀬)旧妻沼町
家は使用人がいたような大きな農家、五女として生まれる
父親は子供たちの教育に熱心な人であった
読み書きそろばん全部できたため、学問の大切さがわかっていた
吟子は兄たちに混じって勉強をするようになった
学問が好きで頭も良かったと言われている
寺子屋へも通うようになり、そこで松本万年に出会う
松本万年は医者であり、その傍ら子供たちに読み書きを教えていた
その万年には娘に荻江という人がいた
荻江は一度嫁いでいたが子供を亡くし離婚して戻ってきていた
その荻江が吟子のことを気に入って吟子に学問を教えることになる
結婚からの転落
吟子が16歳の時、川上村名主の息子と結婚話が出る
父親は願ってもない話なので勝手に了承してしまう
そうして吟子は結婚することになった

当時は父親の命令に逆らえない風潮があったので仕方なくだと思われます。
結婚して故郷を離れた吟子はしばらくすると病気にかかってしまう
下腹部から膿が出て体がふらふらして寝込むことが多くなった
だんだんと症状は悪化し、高熱が出てついには起き上がれなくなってしまった
とは言え夫の両親に寝込んでいることを叱られるのではないかとビクビクする毎日であった
そこで松本万年のことを思い出す
万年に見せれば何かわかるかもしれないという気持ちもあり、
故郷に帰って療養させてほしいとお願いをする
この時吟子は淋病にかかっていた
万年は漢方薬を処方し、吟子にゆっくり休むようにさせた
吟子は実家の居心地がよく体調も回復していった
そして離婚することを決意した

当然ですがこの淋病は夫からもらっているんですね(放送では言わなかった)
吟子は淋病のせいで子供が産めない体になってしまった
そのため夫側の両親もすぐに離婚を承諾した
荻江に「嫁に行き子供を産むだけが女の仕事ではない」と言われ
病気を治し学問に向き合うことにした
吟子は東京で有名な外科医に診てもらうことにした
医者を目指すことに
吟子は東京で西洋医学を学んでいた医師の診断を受けることになった
しかしここでの体験が吟子の医者を目指すきっかけともなる
淋病の症状を確認、治療するためには患部を見せる必要がある
しかし当時女性が男性医師に下半身を見せるなんてことはほとんどなかった
しかもこの時は10人ほどの若い学生たちもいた(もちろんみんな男性)
吟子にとってはこの診断が悪夢のような時間だった
診断が終わると急ぎ病室に戻り布団に閉じこもり大泣きした

なぜ医者は男性だけなのか、
女性の医者が見てくれれば気持ちも違うのにと思ったそうです。
自分が医者になって困っている女性を助けたいと考えるようになる
医師免許取得の厳しい道
当時は徐々にではあるが女性の教育にも関心が出始めていた
津田梅子や大山捨松が岩倉使節団の留学生として渡米などもこの時期の出来事である
しかし女性が医者になるための学校などなかった
そもそも男性ですら西洋医学の知識がほとんどない
そのほとんどは松本万年のように漢方医(東洋医学)
まずは周囲の賛同が全く得られなかった
医者を目指すことを特に身内である母親には大反対された
吟子は子供が産めず離婚して帰ってきたことで世間から笑われている
しかし万年や荻江の説得で最終的には母親も東京へ送り出すことに同意
1875年にはお茶の水大学の前身東京女子師範学校が設立
吟子は東京女子師範学校に入学し、最初の卒業生としてトップの成績で卒業する
そこの教授に好寿医という医学校を紹介してもらえた
しかし生徒は全員男性であった
吟子は男装をしつつ男性に混じって勉強することになる
授業料は元々家族頼みであったが、さすがに医学校の高額な授業料まで無理を言えないため
家庭教師などをやりながらなんとか生計を立てた
1882年に好寿院での勉強を全て終えた
医師になるためには医師開業試験に合格する必要がある
しかし女性に医師免許を与えた実績ないから願書の時点で差し戻されてしまう
それでも吟子はあきらめなかった
実は過去に女性医師がいたことを調べ上げ
前例があることから国は吟子の申し出を退けられなくなった
☞古代律令の解説書「令義解」に女医の記載があった
1884年に吟子は医師国家試験を受けることとなった
1885年の最終試験で吟子は合格し、日本初の女性医師が誕生した
この時吟子は34歳であった
まとめ

前例がないことをやることは周囲からの賛同も得られないし
何より自分が通っている道が正しい道なのかもわからない、、、
そんな中でも信念を曲げずに突き進むことが大事であると思いました。
荻野吟子は日本の女性の地位向上に貢献した人物であり
津田梅子や大山捨松など次々と出てくる著名人のパイオニア的存在であった
医師としての吟子の生涯は決して順風満帆なものではなかったが
その偉業は今なお語る継がれるものとなる
★参考図書