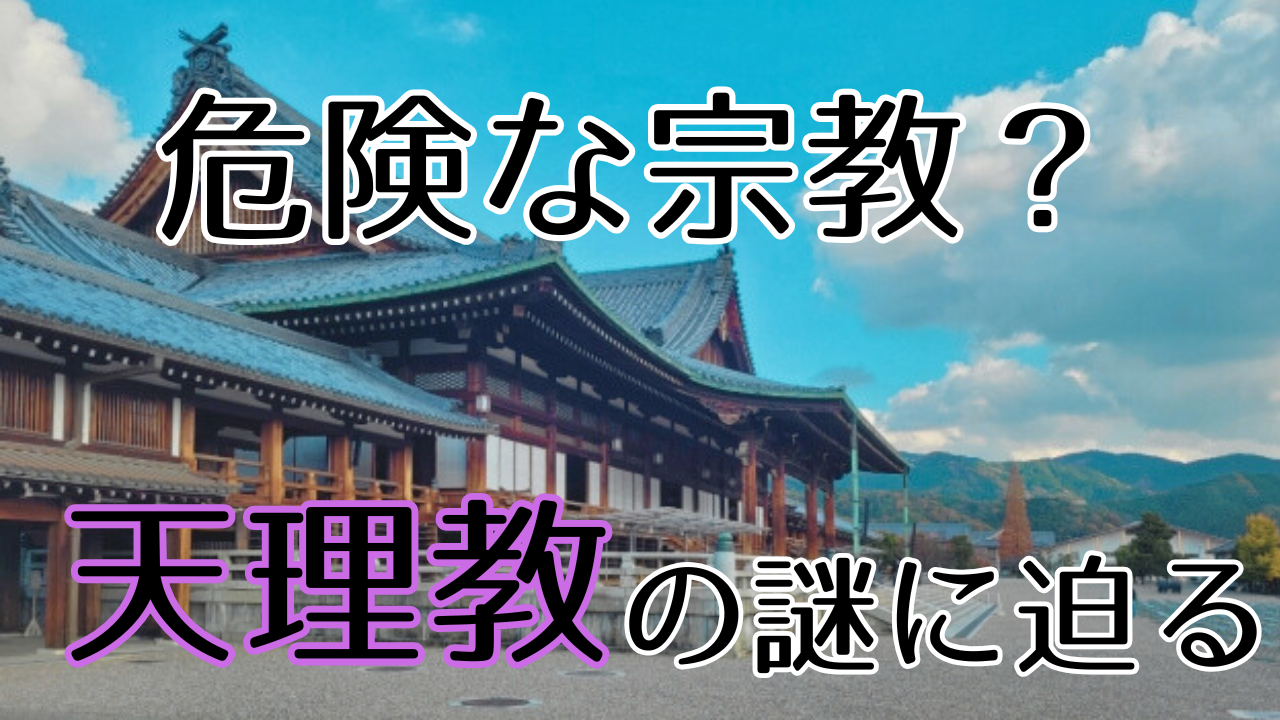■天理教とは
1838年に中山みきを教祖として始まった新興宗教

1837年 大塩平八郎の乱
1840年 アヘン戦争
新興宗教とは言いつつ、結構古い宗教です
【参考】日本の新興宗教設立年
立正佼成会☞1938年
創価学会☞1930年
幸福の科学☞1986年
■天理教の教え、特徴
天理教の神様は天理王命(てんりおうのみこと)
神道や仏教の宗派のように思われることが多いが違う
天理教は天理王命唯一の一神教
「陽気ぐらし」を掲げて人助けを行っている
自己中心的な心遣いではなく他社の幸せを願い助けある心を持つ
天理王命に反することを「ほこり」と呼ぶ
ほこりが溜まると心が汚れるから掃除するように説く
負の感情を持つようなことがあればその心の濁りをきれいにするように保とうとする教え
人の体は神様からの借り物、心は自分自身のもの
怪我したり病気したりするのはどうしようもないこと
人の心は自分で決められる
つまり自分の意志で行動することができる

ちなみに入信は誰でもOKらしいです
■教祖中山みきについて
1798年生まれ
幼い時から浄土宗の信者であった
尼僧になるのが夢だったくらい信仰心が厚かった
1810年に中山善兵衛に嫁ぎ中山みきになる
中山家は豪農であり、お金に困ったりはしなかった。
しかし中山みきは農作業、炊事・洗濯・機織り・子守などで忙しい毎日であった
夫はお金があるからあまり働かずぐうたらしていた
貧しくはないけど日々しんどい生活だった
そこで中山みきは幸福とはいったい何なのか・・・と考えるようになっていた

周りからすればお金持ちの奥さんだし苦労なんてないとも思われていて、誰も自分の本当の心をわかってくれない、、、って感じであったのだと思います
1838年に長男が足をケガして歩けなくなってしまった
当時は祈祷で病気やけがを治していたが、夜遅く祈祷師を呼べなかった
そのため中山みきが祈祷をすることになる

いきなり普通の主婦が祈祷やるなんておかしいんですけど、それだけ中山みきが信心深いことを家族みんなわかっていたので祈祷をしたとされています
その祈祷の中で突如天理王の命が中山みきの体に憑依する
そして中山みきの体をもらい受けることを語り出す
家族は当初大反対で何とか神様に出て行ってもらおうとするが
神様も強引で絶対に引かなかったため、中山家が折れることになる

初めのうちは布教活動も特にせず貧者救済のようなことを行っていました。
徐々に中山みきの教えが受け入れられるようになり、明治時代初期には信者も増えていきました。
しかし、一神教である天理教は天皇制の明治日本下では相容れない存在でした。
国家からの監視対象になり、苦難の道を歩むことになりました。
1887年 中山みきは90歳で亡くなる

社会の動きに柔軟に合わせていったことで、政府からの監視も緩まり今に続く宗教として存続することができました。柔軟に世の中に順応していく姿は宗教としてどうなの・・・と思う反面、誰でも受け入れてくれる器の広い宗教である側面も垣間見れるかと思います。